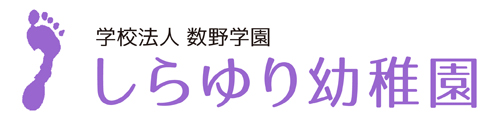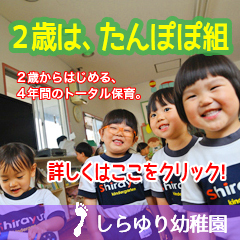はだし保育とは
近年、幼児教育の分野において「からだづくり」についての関心が急速に高まりつつあります。その理由については、人間教育の基礎になる幼児の身体のことが、あまりにも軽視されていたことに対する反省から起こってきているといえます。
本園では、創造的な体育遊びや、水泳、器械運動などの新しい体育カリキュラムをとり入れ、健全な心と身体をもった人間形成の基礎を培うことに特に力を入れています。
その根幹をなすのが「はだし保育」です。
5月から10月の間、園児たちは園庭でも教室でも“はだし”で過ごします。
足を自然の状態にすることで、“つちふまず”の成長につながる・足の裏を刺激することで脳の活性化を促す・風邪をひきにくくなる・足の指を自由に使えるようになる・暑い日でも足が蒸れないといった効果があることが報告されています。
『しらゆり幼稚園』では開園当初から「はだし保育」を取り入れ確かな結果を残しています。
くわしくは冊子『幼児期における心身の研究』をご参照ください。
桜美林大学教授 阿久根英昭先生や玉川大学教授 野田雄二先生、新潟大学名誉教授で新潟脳外科病院ブレーンリサーチセンター所長 生田房弘先生より、『しらゆり幼稚園』の教育に対し共感して頂き、また高い評価を頂いています。
生田先生からは励ましのお手紙を頂戴いたしました。以下、一部抜粋してご紹介します。

数野三郎様、数野朱美様 JUL,17,2002
--(前略)--
私は当地で去る6月15日(土)午前7:50頃、NHK総合で放映されました「はだしの幼稚園教育」という短い放送を眼にし、大変感激し、「これだ!!」と思い、NHKに問合せ、貴園のホームページを開いてもらい見せて戴きました。
私の本来の専門は脳におきる様々な病気の原因やしくみを研究することでしたが、それを知る為に脳の出来方を研究しているうちに、人の心や、科学を研究してもらいたい人間を育てるには、子供の時に、できる丈自然の中で遊ばせるほかにはない筈。
--(中略)--
数野様の様な本物の教育者がおられることを知って、とても嬉しく思ったのでございます。
どうぞ、どこまでもその方向で御盡力をお続け下さいますことを心からご期待申し上げてまいります。
--(後略)--

--(前略)--
私は脳の病気が治る過程を観察してゆくうちに、それは脳が出来てゆく過程を真似ているのだと気付き、以来脳に機能が生まれてゆくメカニズムに入ってゆきました。お手紙にも「一生の基礎を作るのは幼児期」という言葉がみられますが、確かに私も"人間らしさが出来るのは幼児期"にあると考えて参りました。そして、「遊べる子供は知能が高い」。これも真実と存じます。
--(中略)--
大脳だけで140億個もある神経細胞が、夫れぞれが数万個ずつもっているシナプスが夫れぞれ機能を作り上げてゆくのは、それらに外から適切な刺激(それを人は遊びとも言い、教育とも言っているのでしょうが)を与えない限り、機能形成はあり得ないのですから。それによって初めて物が見えるようになり、聞こえるようになってゆく、その根源的なメカニズムに、数野先生方は立脚なさっての教育を実践なさっておられるのだと思うのです。
先生の処で預かって居られる子供さんも、そのお子さんを預けられた家族の方々も皆、本当に幸運な人達と言えましょう。どうぞ、先生の幼稚園の子供さんたちが、今後ますます少しでも多くの自然に触れられること祈ってまいります。
--(後略)--
教育方針
しらゆり幼稚園の教育方針

しらゆり幼稚園では、“はだし保育”を通じて、『遊べる身体』『学べる身体』『治せる身体』の身体づくりと、『やる気』『元気』『根気』『集中力』を育てることを最も重要な教育目標に、日々保育に取り組んでいます。
このために、次の点を特に注意しています。
- 強い体と正しい心を持つように。
- 何事にも一所懸命になれるように。
- 基本的な生活習慣を正しく身に着けるように。
そのために、各家庭と連携をとりながら幼児教育をしたい、と考えています。
『心のかよった保育』『極め細やかな保育』

しらゆり幼稚園では、『心のかよった保育』『極め細やかな保育』を心掛けています。具体的には、園児と先生の朝と帰りのあいさつは、先生がしゃがんで『あくしゅ』をして行います。これは、スキンシップや大人の目線を幼児の目線に合わせるために、また、日常子どもの目線で対応することを心掛けているからです。
『自身のことは自身で』
しらゆり幼稚園では、自分のことは自分自身でできるようにするために、ボタン掛け・ひも結び・脱いだ服の整理・自分の名前を書けるなど毎日の訓練によって指導しています。
『互いに尊敬し、尊重する心』

しらゆり幼稚園では、お互いに尊敬し、尊重する心を育てるために、先生が園児を呼ぶときは、男の子は『くん』、女の子は『さん』で呼んでいます。また、園児同士でも男の子は『くん』、女の子は『さん』で呼び合うよう指導しています。
教育目標
保育の目標
- 健康、安全で幸福な生活のための基本的な生活習慣・態度を育て、健全な心身の基礎を培うようにする。
- 人への愛情や信頼感を育て、自立と共同の態度及び道徳性の芽生えを培うようにする。
- 自然などの身近な事象への興味や関心を育て、それらの対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うようにする。
- 日常生活の中で言葉への興味や関心を育て、喜んで話したり聞いたりする態度を養うようにする。
- 多様な体験を通じて豊かな感性を育て、創造性を豊かにするようにする。
体育の目標
- 活発な動きを伴う体育遊びを多面的に経験させる。
- 自分のからだは自分の意志によって自由にコントロールできる能力を養う。
- 運動に対する欲求を充実させ、情緒の安定を図る。
- 体育遊びを通じて、創造性の芽を育て、自発性をのばす。
- 体育遊びを展開するなかで仲間づくりを推進させる。
教育内容
1.体育教室(毎週2回、1年中実施)
園児は毎日全身を動かして活動しますが、それを体系的にして、1週間に2日、1年間のカリキュラムに沿って運動遊具や運動器具を使いバランスの取れた運動能力の発育を目指します。
2.はだしの運動(5月から10月の間実施)

“はだし”になることで、土の感触を直接感じたり、末端神経を刺激して大脳の発育を助長します。今では、運動と心・脳に関する研究が進み、幼児期の運動が大切であることがわかってきました。
参考までに、本園卒園児の15%は国内屈指の難関大学に進学しています。
3.一輪車(4月から10月の間実施)

年長組になると一輪車に乗ります。運動能力の基本となるバランス感覚を養います。卒園する時には全員が一輪車に乗れるようになります。
4.なわとびあそび・マラソン(11月から3月の間実施)
最良の全身運動です。卒園する時には全員がなわとびができるようになります。また、結び方の練習もします。
5.スイミング(4、5才児が毎週1回、1年中実施)
最良の全身運動です。また、水から受ける皮膚の刺激が呼吸器や循環器などの内臓を強くします。水泳の前後の着替えも大切な学習になります。
6.習字(4、5才児が毎週1回)
4・5才児を対象に週1回実施しています。(外部講師に教わります)
7.オープン保育(月2回実施)

3・4・5才児を縦割りにし、一日一緒に活動します。年少児は年長児に従ったり、年長児は年少児をいたわる心を育てます。
8.しらゆりキンダー鼓隊

年長のゆり組が1988年から脈々と受け継ぐしらゆり幼稚園の伝統です。指導を外部にお願いするのではなく、そのノウハウを園の先生が代々受け継ぎ、ドラムメジャー(指揮者)も園児がつとめ、キーボードを含む全ての楽器を園児たちだけで演奏します。まったく誤魔化しのきかない状況にもかかわらず、見事に演奏する子どもたちは園のたからものです。
成長の記録
しらゆり幼稚園だけが実施している「成長の記録」では、
- ●“つちふます”・体力測定など、成長の記録を各学期ごとに実施しています。
- ●身体測定は毎月実施しています。
- ●顔写真を各学年ごとに写しています。
- ●その他必要な記録を取っています。
“つちふまず”・体力測定・身体測定については、教育の成果と成長の記録として保護者に公開しています。
なお、記録は「成長の記録として」「次にどの様な指導をしたらよいのか」を見極めるための資料として活用しています。
課外教室
希望者を対象に、下記の教室があります。ご家庭の教育方針に合う教室をご利用いただいています。
(別途費用がかかります)
- ヤマハピアノ教室
- 忍者教室
幼児教育は園と家庭の二人三脚
一人一人のお子さまのより望ましい成長のためには、幼稚園と保護者が一体となり相互が理解し信頼しあうこと、また、連絡を取り合うことが大切です。幼稚園と保護者が理解を深める機会として、次の行事があります。
1.個別懇談
4月に全園児を対象に行います。本園では家庭訪問はしておりません。園に来ていただいて懇談をします。
個別懇談以外でも、園でのお子さまの様子を知りたいときや、お子さまのことで相談なさりたいことがありましたら、ご遠慮なく申し出てください。積極的に面談に応じます。ただし、事前に日時の打ち合わせをお願い致します。
2.保育参観

5・6・7・10・11・2月に実施しています。
5月は「給食参観」で、親子で給食を一緒に食べていただきます。
6月は「父の日」に親子レクレーションでゲームをします。
10月は「半日保育参観」で、1日10名前後の保護者に半日参観をしていただきます。クラスの一斉参観では集団の中で本当のお子さまの様子はわかりません。普段「幼稚園でどんな生活をしているか、つぶさにお子さまの活動を見学していただきます。一斉参観は園側の都合で保育の展示にすぎません。ですから本園ではこの様に、普段の保育のありのままの幼稚園を参観していただいています。本園の保育に自信を持っているからです。日程の決定に際しては、事前に保護者に都合の良い日をアンケートして決めています。
参観においで頂いたご家族の感想を紹介します。

園内で遊んだり、室内で歌ったり、元気に楽しんでいる姿を見られてとてもよかったです。先生方の子供に接する態度、気配りがとても感心しました。しらゆり幼稚園は、そういう先生方の教育方針もすばらしいんだなと思います。子供達の笑顔がとても素敵でした。この幼稚園で良かったナ!!と再確認しました。
お昼の時間に思った事ですが、休みの子がいる時など両サイドの席が休みでいない時は、ポツンと一人で食べている姿がかわいそうだナ・・・というか、みんなお弁当を楽しみ、だいたい隣の子と話しながら食べたりしていたので、部屋でいる時、両サイド休みの時はつめてみたらと思っていたらエミ子先生が席をつけてくれたので、そういう心配りがすごいと思いました。

いつも来ている園ですが、(本当にいつもですね)今日はゆっくりと子供達の様子が参観できて楽しかったです。体育教室では皆とても張り切っていて、自分の番になるととても気合がはいっていましたね。踏み切りの動作や列の後につく時の約束事など、大人には当たり前のことも、こうした活動の中で身につけていくんですね。園に来るたびに「なるほど」と思うことばかりです。
つぼみさんの時より一人一人が意思をもって「これをしよう!」と前向きに取り組んでいるように思えました。ありがとうございました。

年長になり、目標に向かってがんばるようになりました。他の年長のお友達も一輪車、うんていとみんなできるようになりたいという気持ちから一生懸命がんばっていました。また、ゆりさんはつぼみさんやたんぽぽのお友達の面倒をよく見てくれていました。しらゆりの子供達は元気で伸び伸びとしていると思いました。泣いたり笑ったりこまったりしながらいろいろなことを考え成長しているのを実感できました。オープン保育も見学できてよかったです。
先生方には、いろいろな子供達を1つにまとめ本当に大変だと思いますが、これからもよろしくお願いいたします。
3.園からのプリント
園からのプリントは園からの重要な連絡事項です。お子さまが「おたよりばさみ」に入れて持ちかえりますので、必ず確認してください。穴をあけたプリントはファイルに保存してください。また、読み損じや記憶違いを防ぐために、読み直しをお願いします。プリントは言葉足らずになりがちです。ご不明なところがありましたら担任にその旨お問い合わせください。
4.運動会・発表会など
お子さまの成長を確かめる良い機会ですので、積極的にご参加ください。
5.連絡帳
お子さまの、ご家庭での様子や園での様子を連絡しあいます。また、成長の様子も知らせあうのに活用しています。
6.電話
4回線入っていますので、繋がらないことはまずありません。
ただし、安全対策のため、電話番号が「通知」されていないと繋がりません。ご利用の電話が非通知に設定されている場合は、頭に「186」を付けておかけください。
FAX:055-253-7072